FASHION MEDIA CHRONICLE #06 時代の“らしさ”とGINZAの“らしさ“を紡ぐ GINZA編集長 矢部光樹子さん
加速するデジタルシフト、多様化する価値観やライフスタイル。目まぐるしく変化する現代社会において、メディアの在り方も日々進化しています。変わり続けることと、変わらないこと。ファッション情報を届けるメディアの「今」と「これから」に迫ります。今回2024年11月号より『GINZA(ギンザ)』編集長を務められている矢部光樹子さんにお話を伺いました。
入社早々に味わったマガジンハウスらしい洗礼!?

—矢部編集長のこれまでの経歴を教えてください。
大学卒業後にマガジンハウスに入社し、最初は『BRUTUS』に配属されました。私は学生時代から『anan』や『CLiQUE(クリーク)』が愛読誌で、他にも『Olive』や赤文字系、親の影響で『クロワッサン』まで、女性誌を幅広く読んでいたので、この人事は本当に驚きました(笑)。どうやら当時のBRUTUS編集長から「いちばんBRUTUSっぽくない子を入れてほしい」という要望があったそうで、見事に当てられてしまったみたいで。その後は『Olive』『BOAO』『anan』の編集部を経験。一番長く在籍したのは『anan』で16年。20代の頃には広告部も経験しました。
—広告部には志願したとか?
志願したわけじゃないです(笑)。でも、入社してすぐ編集部に配属されたので、雑誌というものがどんな仕組みで成り立っているかなど、事業の全体像を知らないまま誌面を作っていたこともあり、広告のことも勉強したいなと感じていたのは事実ですね。若い頃に広告部を経験できたことはとても良かったですね。
—広告部ではどのようなお仕事をされていたのですか?
当時の広告部も変革の時期で、従来の広告代理店さんごとの担当とは別に、雑誌をひとつのブランドとして扱おうという考えが出てきたタイミングでした。そしてひとつの雑誌に専念するチームに所属し、私は『Tarzan』担当になりました。あまり馴染みのない雑誌でしたが、編集部と一緒に新しい媒体資料を作ったり、広告予算を考えたり、メルマガを定期的に発信したりと、仕事はすごく楽しかったですね。編集者とは異なる視点で雑誌を見られましたし、新しいことをゼロから作る経験ができたのはラッキーでした。
読者目線で向き合ってきた『anan』での16年間

—最も長く在籍されたのは学生時代からの愛読誌『anan』だったのですね。
『anan』ってどんなことでもテーマになりうる雑誌なんです。『BRUTUS』もそうですが、特集主義の雑誌。日常生活の中で何か引っかかるものがあった時に、そのテーマ自体が一見『anan』っぽくなくても、こうやれば『anan』らしくなる!という形で企画できればOK。まさに“雑誌らしい雑誌”という感じですね。編集部には、自分のアンテナに引っかかったものを各々が企画し、『anan』という傘のもと自由に突き詰めている雰囲気があって、すごく好きでした。自分の知らなかったことや興味のなかったことが、他の編集部員によって素敵な特集になり、へぇ〜と刺激を受けることも多々ありましたね。
—まさに読む方から作る方になったということですね。
そうですね。でも編集人生で都度実感しているのが、自分はいつまで経っても雑誌好きの“いち読者”だな、ということです。雑誌づくりで迷う時って、作り手目線が強くなりすぎていることが多い気がするんです。その時は、読む人がどう捉えるのだろう、自分は読者に何を受け取って欲しいのだろうという地点に戻るようにしています。まさに『anan』時代は編集としての視点と読者としての視点を行き来しながら、雑誌を作っていた気がします。
『GINZA』の2大柱であるファッションとカルチャー

—『GINZA』の編集長に決まった時の感想を教えてください。
私でいいのかな?という気持ちがありました。ただ、マガジンハウスという会社はまったく違う畑から編集長を引っぱってきたり、異色の掛け合わせを期待する会社なんだよな、と(笑)。私も30年近く編集をやっていますが、その時代や編集長によって、雑誌はどんどん変化するものだと思っています。今までの経験を捨てるわけでもなく、これまでの『GINZA』が築いてきた土台の上に新たな武器を付加できればな、と感じています。
—編集長になられて半年、今後の見通しを教えてください。
『GINZA』の2大柱である“ファッション”と”カルチャー”は変えません。そこを楽しみに読んでくださっている方も多いので。ただ、2大柱といっても実は密接に関係し合っていますし、ファッションそのものがカルチャーの一部であるとも言えます。どちら側から入っても面白い雑誌でありたい。『GINZA』は少し尖ったイメージを持たれがちですが、私としては手に取ってくれた方がソファの上でリラックスして読んで、ホッとしたり、元気になったりする…そんな雑誌でもありたいと思っています。

—矢部編集長になって変化した点などはありますか?
ひとつの表現方法として、写真の選び方や見せ方は変わってくるかと思います。例えば直近のインテリア特集の表紙は、ここ最近の『GINZA』ではなかった感じかもしれません。かっこよさだけでなく、その先に「私もこういう暮らしをしてみたい」とか「こういう人生が待っているといいな」など、前向きな気持ちが湧き上がってくるような誌面にしたいです。編集部員にも、読者が『GINZA』を読んだ後にどういう気持ちになって、どんな行動をしてほしいのかをしっかり考えて作ってほしいと伝えています。
雑誌とWEB、それぞれの情報発信の場を大切に
—今後はWEBでの情報発信にも力を入れていくと伺いました。
現代においてSNSを含むデジタルコミュニケーションは不可欠です。ただ、それは情報を取るプラットフォームが拡大しているだけで、好きなものが変化しているわけではありません。雑誌であれ、SNSであれ、『GINZA』発信のものを好きな人は確実にいると実感していますし、最近はSNSきっかけで雑誌を買ってくれる若い方も増えました。SNSや動画でも自然と“『GINZA』らしさ”が出ているようで、よくブランドさんからも「『GINZA』ゾーンに入ったのが分かる」と言っていただけます。本当にありがたいことですが、それは同時に編集部員が常に意識していることでもあります。例えば人選でも「なんとしてでも新鮮な人を見つけたい」というような負けん気の強さや、企画に対する粘り強さがあります。タイアップでもブランドさんから『GINZA』らしくしていただければ大丈夫です、と言っていただけることが多いのは強みです。それはこれまでも他と同じことはやらないという強い意志を持ってきた結果だと思っています。その独特の世界観は大事にしながら、あと雑誌は雑誌なりに、雑誌ならではの面白さも大切にしています。

—例えばどんなことでしょうか?
これも直近のインテリア特集の話ですが、タイトルは“やっぱり家が好き”にしました。お分かりになる方もいると思いますが、それに絡めて本誌内のいたる所に“猫”を仕込んでいます。たとえ気付かれなかったとしても、そんなクスッと笑える仕掛けなど、雑誌だからこその遊び心は忘れないようにしています。いずれにせよ、デジタルと本誌でその根底部分は共通しているのが大事。やっぱり雑誌は家でゆっくり読みたいし、SNSはサッと検索して欲しい情報に早く辿り着きたいもの。それぞれの媒体で何を求められているか、意識しながらアウトプットを変えています。

新たな試みで“GINZAゾーン”の拡張を目指して
—今後チャレンジしていきたいことを教えてください。
『GINZA』で取り上げられない話題はないと思っています。例えば、“旅”や“食”、ファッションに紐づけた“ビューティ”など、最近は深掘りしてこなかったカテゴリーにも挑戦したいですね。あとはやはり動画の強化です。ここも本誌とデジタルとの乖離は避けたいので、あまり境界線を意識せず、本誌の撮影の延長で動画を撮るなど新しい試みも実践中です。
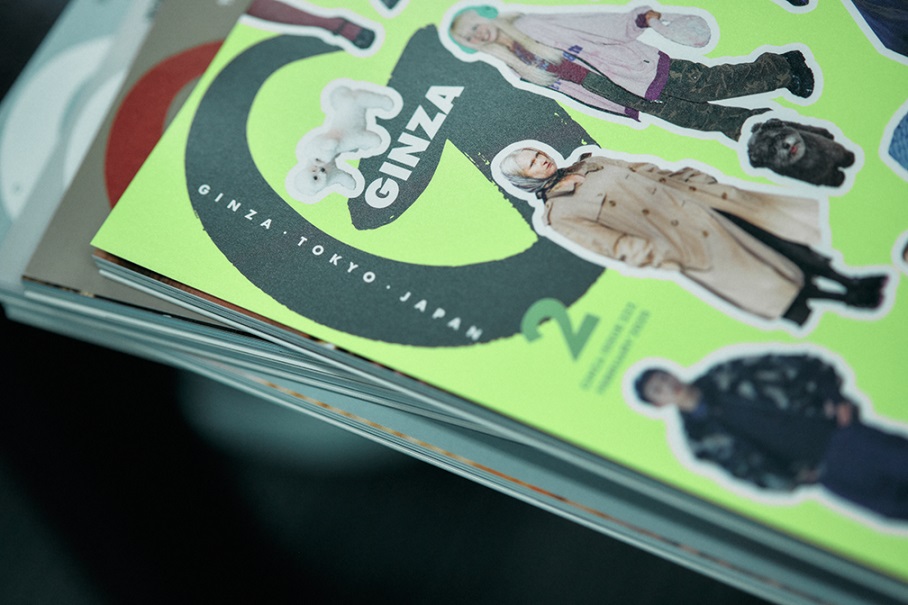
あとは、これは創刊以来続いていることですが、雑誌名でもある通り、しっかりと東京の銀座発信ということを意識すること。『GINZA』のロゴには“GINZA・TOKYO・JAPAN”と書いてあります。もちろん東京が一番とか、すごいとか、そういう意味ではなく、私たちが暮らし働いているのが東京であり、そこにいる編集者がリアルに感じたことを世界に向けて表現していく。それこそが読者やユーザーと温度感を共有できるポイントだと思っています。東京をどう捉えるかは、その時代によって違うと思うので、そこをきちんと捉えて、『GINZA』の“らしさ”を磨いていきたいと思います。
.jpg)
矢部光樹子さん 東京都出身。1998年マガジンハウス入社。『BRUTUS』『Olive』広告部『anan』『BOAO』『anan』でのキャリアを経て、2023年12月に『GINZA』の副編集長に就任。2024年6月より現職。仕事の合間の楽しみは、ドラマの一気見、ライブに出かけること、ライブにかこつけての小旅行。
Photo:Mizuho Takamura
Text:Asako Fujita
-

FASHION MEDIA CHRONICLE #12 ジャーナリズムを根幹に、本質的な価値を届ける。『Esquire』日本版編集長 近藤智之さん
2025.10.27
Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #11 信念を曲げない覚悟が、信頼をつくる。『Precious』の品格と矜持 Precious編集長 池永裕子さん
2025.8.25
Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #10 美容コア層からキッズ、メンズまで。拡張し続ける『美的』の世界 美的編集長 中野瑠美さん
2025.8.4
Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #09 編集長という肩書きは、もういらなくなる。 NYLON JAPAN編集長 戸川貴詞さん
2025.6.30
Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #08 アメリカ西海岸へのブレない憧れは、時代や世代を超える Safari編集長 園部仁さん
2025.4.10
Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #07 地球上のすべてのカルチャーを包括する BRUTUS編集長 田島朗さん
2025.3.21
Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #05 ウェルネス情報を楽しく、賢く、スピーディーに Women‘s Health編集長 嶋内瑠璃子さん
2024.11.1
Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #04/柔軟な価値観を持つ世代とシームレスにつながる MEN’S NON-NO ブランド統括・WEB編集長 丸山 真人さん(写真:右) MEN’S NON-NO プリント版編集長 吉﨑 哲一郎さん(写真:左)
2024.9.2
Media
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)