「美容に“人にも地球にもやさしいコスメ”という選択肢を」 使い手と作り手をつなぐ、新しいコスメのあり方 サステナブルコスメアワード審査委員長 岸紅子さん
Fashion × Sustainabilityをテーマに、ファッション業界で活躍するトップランナーの方々とファッションの未来や可能性、これからのビジネスのヒントを探る連載企画。今回はファッションとは切っても切り離せない美容・コスメのフィールドにフォーカスします。2019年にスタートした国内唯一の化粧品・ファイントイレタリー分野におけるSDGs視点でのアワード『サステナブルコスメアワード』。その発起人であり審査委員長の岸紅子さんに、美容×サステナビリティの現在地を伺いました。
美容は高いレベルの健康

―まずはじめに、岸さんの経歴を教えてください。
学生時代にファッション雑誌の読者モデルとして活動し始めたのがスタートです。出演だけでなく美容ジャーナリストとしても関わるようになり、美容ブランドや美容誌の立ち上げなどにも携わりました。そして大学卒業と同時に美容のマーケティング会社を起業し、オンライン調査やミステリーショッパーなどを派遣したりしていました。お陰様ですごく忙しくさせていただいたのですが、忙しすぎて体調を崩してしまいました。それでも若さにかまけて薬を飲みながら続けていたのですが、いよいよごまかしが効かなくなってしまったのが20代後半。仕事中に倒れ、外にも出られない状態になりました。30歳を目前に一旦全てをさらにして、自分の体や生活を見直さなくてはいけなくなりました。それが最初の試練。そこからホリスティックビューティに目覚めていきました。
―ご自身の苦難や実体験がベースになっているのですね。
それまで“頑張って働く”ということが普通だと思っていました。でも、それが思っている以上に体や心が乱れる原因になっていたんです。私がそうなったのだから、きっと多くの女性が同じことに陥る可能性があると思い、少しでも助けになれればと2006年にNPO法人日本ホリスティックビューティ協会を立ち上げました。
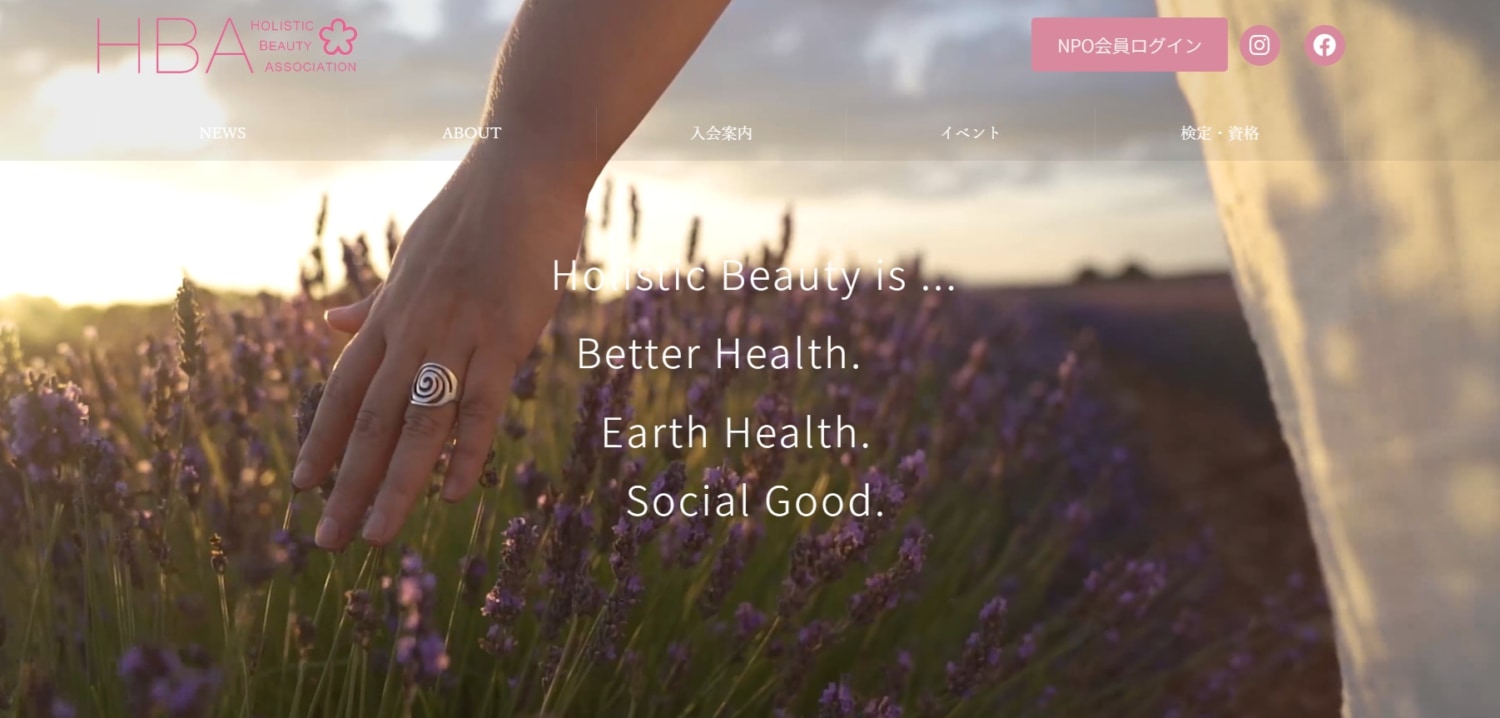
NPO法人日本ホリスティックビューティ協会のホームページ
―ホリスティックビューティとはなんでしょうか?
人が本来持つ美しさって、スガタ、ココロ、カラダが包括的(ホリスティック)につながりあって成り立つものです。私たちは「美容は高いレベルの健康」だと定義しています。例えば顔色が悪くて可愛いとか、具合悪そうで可愛い、ってないですよね?美しさはイキイキと生命感がある=健康的であるというのが基盤になります。美容や健康のために、まずは自分の体や心を知って、メンテナンスできるようにしようね、と提唱することが私たちの役目。でもそれを追求していくと、自ずと環境にもつながってくるんです。
自分の健康が社会貢献活動になる!?
―美容が環境につながる、とはどんなことでしょうか?
自分が健康になるための食べ物や生活習慣を選択していくと、結果的にいわゆるエコ活動と呼ばれるものにつながっていきます。例えば早寝早起きをしようとか、暴飲暴食をやめようとか、体に良いものを食べようとすると、必然的に無駄な消費をしなくなったり、オーガニックな食材を選ぶようになりますよね。環境活動どころか、社会活動にもなるんです。

例えば自分が長患いせずに“ピンピンコロリ”(病気に苦しむことなく、元気に長生きし、最後に寝込まずに静かに死ぬこと)できたとしましょう。現在の日本人ひとりに対して生涯でかかる医療費は約2700万円と言われています。それを私が1700万円ぐらいに留めることができたら、未来に1000万円ほど献金できたことになる。なぜなら、その平均2700万円の医療費のうち、自己負担は1~3割。残りは国が補助していますよね。でも財源は足りないので国債を発行して未来から借金しています。そのつけを払うのは未来の子供達。私たちは彼らのクレジットカードを借りて自分の医療費を払っているようなものです。それであれば、私が医療費の平均を下回って生涯を終えられたら、未来の子供達の負担を軽減できたことになる。
―なるほど。健康であることが、結果的に未来の財源負担を軽減することになるということですね。
医療は人が生きていく上でたくさんお金がかかる分野のひとつです。よく、「社会に貢献できることって何がありますか?」と聞かれたりするのですが、その都度「あなたが健康でいてください」と応えています。早寝早起きして、できるだけ旬なものを食べる。それが社会貢献になるんです、と。
―確かに最近、社会貢献や企業の社会的責任という言葉をよく耳にします。
それらの目的が「社会や地球を良くするために」ということは言葉では理解できますが、実感するにはあまりにも壮大すぎますよね。ましてや社会や地球が抱えている課題の全てを自分で背負う必要はないんです。あくまで自分基準でよくて、自分を健康にすることが社会や地球の健康につながっている、と理解できれば、あとは自分を健康に保つための選択をすればいい。それをみんなでやっていけば、自ずと社会全体がいい方向に進むはずです。なので、自分のウェルネスを大切にするという考えがもっともっと広がってくれればいいなと思っています。
2030年に終了する、サステナブルコスメアワード
―ではサステナブルコスメアワードについて教えてください。
2016年に環境省のアンバサダーに任命され、そこから個人的にも環境意識が高まったのは事実です。サステナブルをキーワードに美容業界でできることってなんだろう、と考え、アンバサダーの仲間たちと語り合う中で、2019年に「人にも地球にもやさしいコスメ」をテーマにサステナブルコスメアワードを立ち上げました。今年で6年目、もともとはコスメ=化粧品にフォーカスしていましたが、現在ではランドリーやハウスクリーニング、サニタリーなどにも対象を広げています。そしてパンフレットにも記載していますが、2030年には終了する、と断言しています(笑)。それはその頃には「人にも地球にもやさしいコスメ」が当たり前になっているはず、という願いも込めています。

―具体的にどのようなアワードなのでしょうか?
まずメーカーさんにSDGsの17項目に関わる90項目ほどの質問を投げかけさせていただきます。その質問の範囲は製品に使われている成分はもちろん、原料が作られる畑のことから実際にものができる工場や流通、消費者の手に渡って廃棄されるところまで、いわゆるコスメの一生を通して、どういう活動をされているか、を網羅しています。基本的には加点方式のポイント制で、高いものから第一次審査を通過し、第二次審査は官能テスト。審査員の方々に実際に製品を触っていただき、感想をもらいつつ、最終的に総合評価で各賞を決定しています。コスメおよびファイントイレタリー分野では、国内で唯一サプライチェーンを通じてのSDGs視点で審査基準を制定したアワードです。
―加点方式というところがユニークですね。
はい、いわゆる“認証”というものは、「ここまでをやってくださいね」という基準を作って、そこを満たしているかどうかを検査員が赴いて判断します。その検査員の派遣費などもメーカー側が負担するので、認証を取るためには膨大な費用がかかります。しかも製品ごとにかかってくるので、それを負担できる体力のあるメーカーさんは一握りです。でも草の根で見ていくと、日本には本当に素晴らしい活動をされているメーカーさんがたくさんあります。それらのメーカーさんたちに光をあてたい、という志のもと、“認証”ではなく“アワード”、減点方式ではなく加点方式にして、費用を抑えつつ運営しています。

サステナブルコスメアワード第二次審査の様子
コスメが地域をエンパワーする
―素晴らしい活動をされているコスメメーカーさんとはどんなことをされているんですか?
例えば、地域課題になっている耕作放棄地を再活用して作られているコスメがあります。日本各地で馴染み深い緑茶ですが、剪定されないお茶畑は藪になってしまいます。それを切るための予算を地方自治体や農家が捻出するためには“切る理由”が必要になります。一方、お茶の実を獲って圧搾すると上質なオイルができます。それを原料としたコスメを作れば、販売して伐採費用に還元していくということができるわけです。竹も同じです。竹林が手付かずになっていると地盤が弱くなり土砂災害のリスクが高まります。でも竹からは一年に一度だけ竹水(ちくすい)という水が獲れます。その竹水を検査してみたら、すごい抗酸化作用がありました。それを使ってコスメを作れば、竹を伐採する理由にもなります。日本が抱えている農業課題に対するソリューションを開発しながら、誰かの美容のためにもなる。そんな素敵な循環を作っているメーカーさんたちが日本にはたくさんいます。

2024年度サステナブルコスメアワード表彰式の様子
でも、そういうメーカーさんは本当に利益ギリギリのところでやっています。先ほどお話をしたような認証をとるための予算なんてあるはずもないんです。また、そういう背景があるので、原料が潤沢にあるわけでもない。いわゆる一般流通に乗せられるほど大量かつ安定的に生産できないので、脚光を浴びる機会が少ない。だからこそ、そういうメーカーさんに光を当てたいし、「このコスメがあってよかった」と地域の方々に思われるコスメがあってもいいんじゃないか?と。そういうコスメのあり方もあるんだよ、と世の中に投げかけたい。まさに文字通り草の根運動なんですが。
―最近のマーケットの反応はいかがですか?
かなり良い反響があります。昨今、サステナビリティの概念が広がっている影響もあると思いますが、消費者の意識が変わってきていることを実感します。というのも、このプロジェクトに賛同してくれる一般流通さんも増えてきました。今年もサステナブルコスメアワード主導で再循環をテーマに、パッケージに傷があるものや消費期限が一般流通では受けてもらえない製品を、廃棄するのではなく少し安く提供する企画を実施しました。結果、約1,500個のコスメアイテムをレスキューでき、参加したメーカーさんたちにとってはかなり大きいメリットになりました。

何よりもそれを小売側が賛同して、一緒にやってくれたことが大きな一歩でした。もちろん日本の小売や販売側の厳格なレギュレーションがあるからこそ、クオリティの高いサービスが提供できているのは事実ですが、その基準には乗れないけど、素晴らしく意義のある製品もたくさんあり、そういうストーリーに対する消費者の理解が深まっている結果だと思います。消費者の意識が変われば、小売側も変わらざるを得ないですから。
クリエイターたちが共感するサステナブルなものづくり
もうひとつ、消費者の意識が変わってきているきっかけになっているのが、影響力のあるクリエイターや著名人の方々が本気でサステナブルなものづくりに参入しているムーブメントがあると思います。彼ら彼女らのものづくりに対する姿勢は素晴らしく、日本各地の風土に合わせて、昔から残っているものを有効活用したり、作り手の人たちとしっかり寄り添いながら、製品をプロデュースされています。クリエイター視点からしても、地域に根ざしたものづくりや、ストーリーのあるものづくりというものに価値を見出している気がします。この流れをもう少し大きな渦にしていきたいと思っています。

もちろんお金が大事じゃないと言っているわけではなく、いい循環を作るためにも、お金は必要です。ただ、誰かに富が偏りすぎると循環が生まれにくい。もともと予算もない中、善意や地域のためにやっていたことでしょうからもう少しショーアップできればいいと思っています。また、オーガニックコスメはファッションに比べれば製造過程もそこまで複雑ではないので、誰がどこで作っているかなど、細かいトレーサビリティーも追跡できます。作り手の顔が見えるコスメ、そういうものが大手メーカーさんからも出てくるともっと美容業界は盛り上がるはずです。
―今後の展望は何かございますか?
サステナブルコスメアワードのメンバーとは、生鮮食品のようにシーズナルなコスメがあってもいいよね、と話しています。売れるコスメを作る、というよりも、コスメのあり方やコスメの消費の仕方を、より柔軟に捉え、拡張させること。コスメが美容のためだけでなく、地域をエンパワーするものになったり、旅の行き先になったり、そこにあるコミュニティへの入り口になったりする。そんな多様なコスメのあり方を世の中に示していければいいなと思っています。そして自分を健康にするための選択肢がたくさん増えれば、消費者も楽しいだろうし、それが結果的に社会も地球にもやさしい、大きなサステナビリティの潮流になると信じています。
-1500x1000.jpg)
岸紅子さん 東京・渋谷区生まれ。一児の母。自身や家族の闘病経験をもとに、2006年にNPO法人日本ホリスティックビューティ協会を設立。女性の心と体のセルフケアを提唱すると共に、自らも自然治癒力や免疫力を引き出すためのウェルネス講座も開催。2016年より環境省のアンバサダーも務め、ライフスタイルに合わせたSDGsアクションを多く提言。2019年にサステナブルコスメアワードを立ち上げ、審査委員長を歴任している。
Photo: Shota Kikuchi
-

「自分の笑顔を守ることが誰かを守ることにつながる」 人気モデルがたどり着いた自分らしい社会とのつながりかた モデル/デザイナー マリエさん
2025.4.22
Sustainability -

「工芸は日本古来のサステナブルなものづくり産業」全国800のメーカーとともに紡ぐ“当たり前”をスタンダードに 中川政七商店 千石あやさん
2025.2.3
Sustainability -

「歴史は過ぎ去ったものではなく、未来への起点」人を潤わせる仕事、美容師が社会を潤わせるためにできること TWIGGY.主宰・松浦美穂さん
2025.1.15
Sustainability -

「地球というひとつの大きな生命体を意識する」 宇宙、旅、ファッション、自分の“大好き”がつながっていく感覚 モデルNOMAさん
2024.11.20
Sustainability -

「新しい価値観が生まれる瞬間を目撃せよ」ファッション編集者がサステナビリティに夢中になる理由 サステナビリティ・ディレクター向千鶴さん
2024.9.2
Sustainability -

銀座英國屋×BRING/オーダーメイド×リサイクルで理想の循環型社会を目指す
2024.5.7
Sustainability -

草木染めを体験しながら環境問題を考えよう!小学生に向けてTHE GOAL SDGsワークショップを開催
2024.2.10
SustainabilityAction -

スタイリスト・EDISTORIAL STORE オーナー 小沢宏さん/DEAD STOCKに新たな息吹を与え、LIVE STOCKとして蘇らせる
2023.12.4
Sustainability
-1500x1000.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)

.jpg)